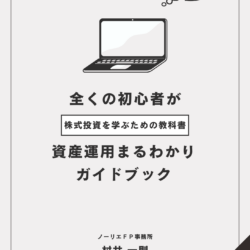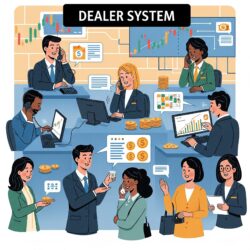生活保護に対する偏見や誤解
皆さんは「生活保護」という言葉を聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか?ネガティブな印象を持つ方も多いかもしれませんが、生活保護は、国民が最低限の生活を送るための「セーフティネット」としての役割を担っています。本記事では、生活保護制度の基本的な仕組みや申請方法、注意点などをファイナンシャルプランナーの視点から解説します。
最低限生活費を支援する生活保護
日本には、3度の食事が満足に取れず経済的・精神的に追い込まれている国民を保護する生活保護制度があります。
生活保護は、働けない、働いても生活することができないなどの理由で、最低限の生活を営むことが困難な方に対して、国と地方公共団体が生活費を支給する制度です。
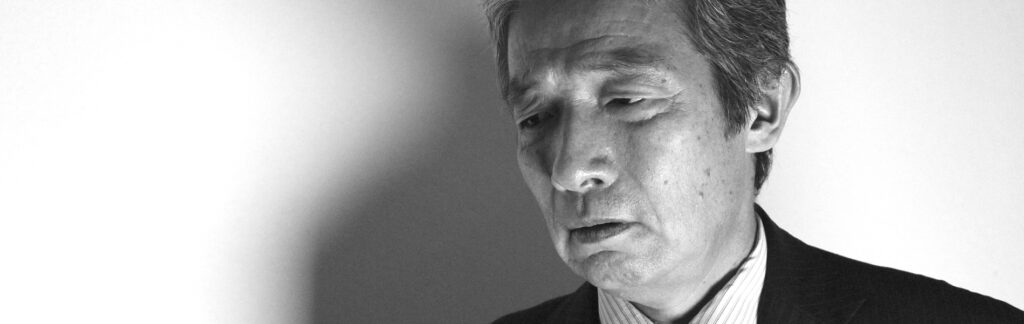
1日3度の食事がとれないぐらい困窮していなら生活保護が受けられる
さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、憲法25条で保障された健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するため、生活保護法第2条「法律の定める要件を満たす限り、この法律で保護を無差別平等に受けることができる。」と定めています。
生活保護制度は、経済的に困窮している方々が最低限度の生活を営むために、国が必要な援助を行う制度です。この制度は憲法第25条に基づき、「すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するために設けられています。
生活保護は、収入や資産が一定基準を下回る方に対して、生活費、医療費、教育費などの支援を提供します。扶助の種類は以下の通りです。
- 生活扶助: 日常生活に必要な費用
- 住宅扶助: 家賃や住宅維持費
- 医療扶助: 医療費全額の支援
- 教育扶助: 子どもの学用品や給食費
- 介護扶助: 介護サービスの費用
- 出産扶助: 出産にかかる費用
- 葬祭扶助: 葬儀にかかる費用
生活保護は国民の権利
- 健康で文化的な最低限度の生活の保障: 食料、衣料、住居など、人間らしい生活を送るために必要なものを保障します。
- 自立の促進: 働く能力がある場合は、就労支援を行い、自立を促します。
生活保護と聞くと,ネガティブなイメージを持たれる方が少なくありませんが、国のホームページ「厚生労働省」でも、「ためらわず相談」を呼び掛けている国の制度です。
生活保護の対象の要件
受給するには、財産や家財を処分したり、親戚などからの援助が得られない状態まで困窮し、万策尽くした後のイメージがありますが、最低生活が維持出来ない状態であれば、本来生活保護を正当に受けることができます。
生活保護を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 日本に住所を有する国民であること
- 資産がほとんどないこと
- 働けない、働いても生活できないこと
申請の流れ
生活保護を受けるためには、市区町村の福祉事務所で申請を行います。以下が基本的な手続きの流れです。
- 相談: 福祉事務所で担当者に現状を相談します。
- 申請書の提出: 必要書類を準備し、生活保護の申請を行います。
- 調査: 福祉事務所が収入や資産、生活状況を調査します。
- 決定: 支給の可否が決定され、支給内容が通知されます。
申請に必要な書類としては、収入証明書、資産状況がわかる通帳や証書、家計簿などがあります。

生活保護は、私たちの社会における大切なセーフティーネットです。制度を正しく理解し、必要なときには遠慮なく利用することが、生活を立て直す第一歩となります。今後もこの制度が、困難な状況にある方々を支える役割を果たし続けるために、私たち一人ひとりが制度への理解を深めていきましょう。