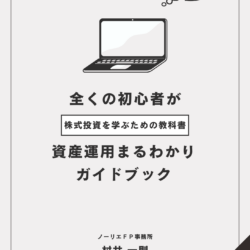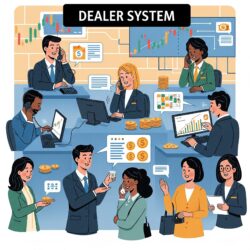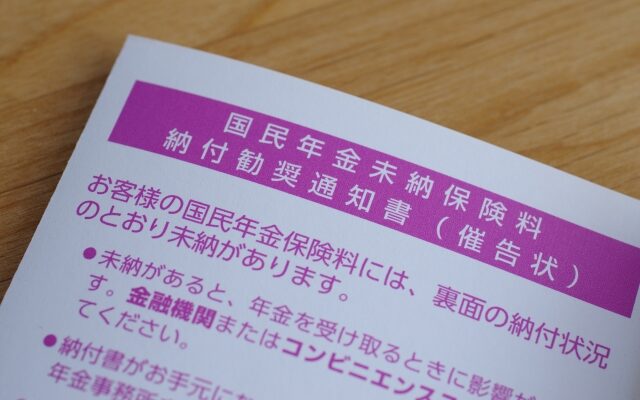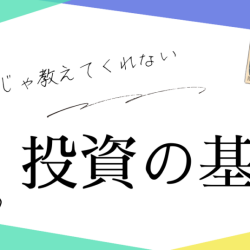第1号被保険者が納める国民年金の保険料には、必ず納めなければならない定額保険料と、任意で納めることができる付加保険料があります。
定額保険料
定額保険料の保険料額は、2005年以降、2004年の制度改正で定められた保険料水準に、その年度の保険料改定率を乗じて得た額とされます。
2024年4月から2025年3月までは月額16,980円となります。
付加保険料
付加保険料の額は、月額400円で、定額保険料に上乗せして納めます。納めた付加保険料の額に応じて、将来、付加年金を受け取ることができます。付加年金は、2階建て部分がない第1号被保険者の年金額に+αすることを目的としたもので、その年金額(年額)は「納付した月数×200円」です。
| 定額保険料 (2024年度) | 月額16,980円 |
|---|---|
| 付加保険料 | 月額400円 |
付加保険料を納めることができるのは第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳以上の人を除く)のみです。ただし、国民年金基金の加入者や保険料免除制度等の該当者は付加保険料を納めることができません。また、定額保険料に上乗せして納めるため定額保険料を滞納している間は、付加保険料を納めることはできません。
ただし、個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は同時加入が可能です。
被保険者別の保険料の納付
国民年金保険料は、被保険者の種別によって納付方法が異なります。
第1号被保険者と保険料の納付
国民年金の第1号被保険者は、毎月の保険料を、原則として翌月の末日までに納めなければなりません。付加保険料の納付を申し出ている場合は、付加保険料も納めます。なお、定額保険料には早割制度・前納制度があり、これらを利用すると保険料が安くなります。
国民年金の保険料は被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納める必要があります。ただし、経済的な理由で保険料の納付が難しい場合等には、保険料の免除や納付の猶予を申請することができます。また、第1号被保険者本人が出産を行った際は、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
第2号被保険者・第3号被保険者と保険料の納付
第2号被保険者と第3号被保険者は、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。これは、第2号被保険者が保険料を納めている厚生年金から、第3号被保険者の分も含めて、国民年金に基礎年金拠出金を納付しているためです。
保険料の納付方法
国民年金の保険料は、金融機関などの窓口や、コンビニエンスストアなどで納付することができます。口座振替やクレジットカードによる納付も可能です。
早割制度
口座振替により保険料の納付を行う場合、保険料の引落しを翌月末ではなく、当月末にすると、2024年度は16,920円で毎月60円ずつ割引となります。なお、現金またはクレジットカードによる納付の場合は、早割制度の適用を受けることはできません。
前納制度
前納制度には、6か月分・1年分・2年分の前納があり、現金またはクレジットカードによる納付と口座振替による納付では、割引額が異なります。最も割引額が大きくなるのは、2年分を口座振替で前納した場合です。
【2024年度の国民年金前納割引制度(口座振替 前納)】
| 6か月前納 | 1年前納 | 2年前納 | |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 100,720円 (1,160円) | 199,490円 (4,270円) | 397,290円 (16,590円) |
( )は毎月現金で納める場合と比較した割引額
【2024年度の国民年金前納割引制度(現金払い 前納)】
現金払いで、1年度分を前納すると、年間3,620円、2年度分の前納なら、2年分で15,290円の割引となります。
| 6か月前納 | 1年前納 | 2年前納 | |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 101,050円 (830円) | 200,140円 (3,620円) | 398,590円 (15,290円) |
( )は毎月現金で納める場合と比較した割引額
国民年金保険料の納付の時効
国民年金保険料の納付期限から2年を経過すると時効により納付できなくなるため、未納の保険料がある場合は、できるだけ早く対応することが重要です。ただし、いくつかの例外的な救済措置もあります。
たとえば、追納制度を利用することで、特定の条件を満たす期間の保険料をさかのぼって納付できる場合があります。追納は、過去に保険料の免除や猶予を受けていた期間に対して適用され、原則として10年以内であれば追納が可能です。ただし、追納には追加の加算額が発生することがあります。
また、経済的な理由などで納付が難しい場合には、免除制度や納付猶予制度を申請することも検討してください。これらの制度は、一定の所得基準を満たす場合に利用でき、将来の年金額を一定程度保障する役割もあります。
さらに、学生の方は、学生納付特例制度を利用することで、在学中の保険料の納付を猶予し、卒業後に追納することが可能です。この制度を利用すれば、将来の年金受給資格を確保することができます。
保険料の未納が続くと、将来受け取れる年金額に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、早めに年金事務所や専門家に相談し、適切な手続きを進めることが大切です。