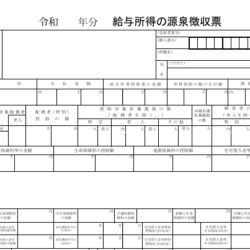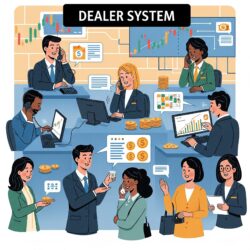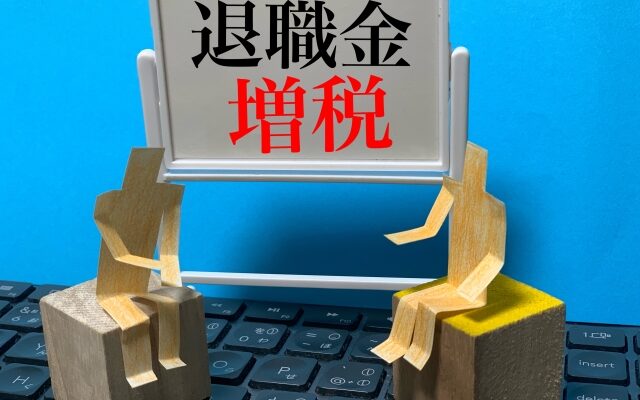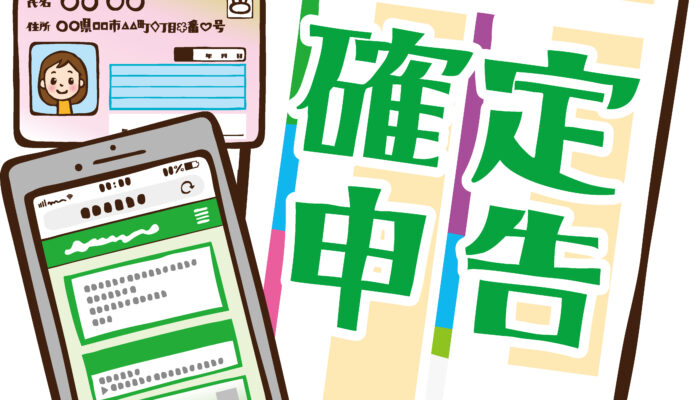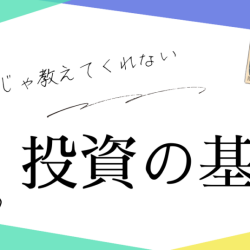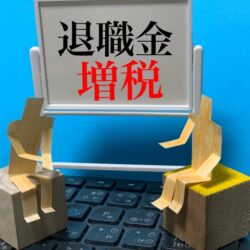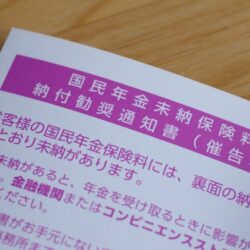投函質問
2年後に退職金を受け取る予定です。iDeCoは加入期間が足りないため、退職時の2年後に一括受け取りを考えています。(iDeCoは300万ぐらいまで成長する想定)
この場合のiDeCoにかかる税金の計算方法を教えてください。
退職金を受け取る際、税金の負担を抑えることができる「退職所得控除」を適用できます。さらに、退職後にiDeCo(個人型確定拠出年金)を一括で受け取る場合も、税制の影響を考えることが重要です。今回は、2年後に退職金を受け取り、その後にiDeCoを一括受け取りするケースを解説します。
退職金の受け取りと税金
退職金は「退職所得」として課税され、所得税法に基づき、退職所得控除が適用されます。控除額は勤続年数によって変動しますが、長く勤務しているほど控除額が大きくなり、課税対象額が抑えられます。計算式は以下の通りです
- 勤続年数が20年以下:40万円 × 勤続年数
- 勤続年数が20年を超える:70万円 ×(勤続年数 − 20年)+ 800万円
課税所得はこの控除後の額の1/2で計算されるため、退職金受け取り時の税負担は比較的低く抑えられます。
iDeCoの受け取り方と税金
iDeCoを一括で受け取る場合、受取金額は「退職所得」として計算され、退職金と同様の退職所得控除が適用されます。ただし、同じ年に退職金とiDeCoを受け取ると、退職所得控除という非課税枠の重複利用ができず、控除がまとめて適用されるため、控除額が分散され、税負担が大きくなることがあります。
そのため、退職金受け取りとiDeCoの一括受け取りを異なる年に分けて受け取ることが望ましいとされています。これにより、双方の受け取りに個別の控除を適用でき、税金を最小限に抑えることができます。
具体的なシミュレーション例
仮に相談者の案件で、退職時に退職金を受け取り、その2年後にiDeCoで270万円を一括受け取るとします。なお、退職金の控除とiDeCoの控除では、『19年ルール』の影響を受けるので、退職所得控除の調整が行われます。
勤続年数30年で退職金を2,000万円、iDeCo10年で270万円の一括受け取りでシミレーションしてみます。
まずは、退職金にかかる税金を計算します。退職金の控除額は「800万円+70万円×(30年-20年)=1500万円」、よって退職所得は「(2000万円-1500万円)×1/2=250万円」です。
退職金にかかる所得税は「(250万円×所得税率10%-控除額9万7500円)×102.1%=約15万2000円」、住民税は「250万円×10%=25万円」です。よって、退職金にかかる税金は約40万円となります。
次に、iDeCoにかかる税金を計算します。退職金支給後の退職金等は19年間は制限を受ける「19年以内」ルールが適用されるため、iDeCoの加入年数から雇用期間と重複する部分の控除額を除く必要があります。
よってiDeCoの退職所得控除額は、「40万円×10年(加入期間)-40万円×8年(重複期間)=80万円」となります。この退職所得は「(270万円-80万円)×1/2=95万円」です。
これにかかる所得税は(95万円×5%)×102.1%=約4万8千円、住民税は95万円×10%=9万5千円ですので、iDeCoにかかる税金は約14万円となります。
以上により、退職金とiDeCoにかかる税金は合わせて約54万円です。
参考までに、税負担が最も軽減できる受け取り方としては先に、iDeCoを受け取り、5年後に退職金を受け取るパターンの方が退職所得控除額(非課税)を効果的に使える可能性があります。詳しく学びたい方は会員限定コンテンツをご覧ください。
ポイントまとめ
- 退職金とiDeCoを同じ年に受け取ると控除額がまとめて適用されるので税金の負担が重くなる。
- なるべく異なる年に受け取ることで、退職所得控除を適用恩恵が受けられる可能性がある。
- 税務上の負担を軽減するため、受け取り時期を調整することが重要。
今後のライフプランにおいて、退職金やiDeCoの受け取り方を計画的に検討し、最大限の税制優遇を活用しましょう。アドバイザーなどの専門家の助言を得ることで、最適な受け取り戦略を立てることができます。